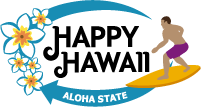ハワイのファッションといえばアロハシャツ!
カラフルで、涼しげで、せっかく南の国へ旅行に行くならコレを着て気分をあげたいところですよね。でも考えてみると、どうしてこのシャツがハワイの代表的なファッションとなったのか不思議ではありませんか?
実はハワイシャツの誕生と流行には日本が密接に関係しています。そこで今回はアロハシャツについて、その成り立ちや歴史について詳しくご説明していきたいと思います!
アロハシャツとは

アロハシャツはトロピカルなモチーフや和柄をメインにしたカラフルな半袖開襟シャツのこと。素材としてはシルクやレーヨン、ポリエステル、綿などが用いられ、夏の定番ファッションとして日本でも大人気です。
そもそも「アロハ」というのはハワイ語で「好意」「愛情」などポジティブな意味をもつ言葉で、ハワイでは挨拶としても使われます。そんな言葉をシャツの名称にしているだけあって、アロハシャツは明るいイメージや常夏のイメージを連想させるようなデザインをしています。
柄はパイナップルなどの南国フルーツをモチーフにしているものやフラダンスを踊る女性など、シャツによってさまざまな種類があり、特に「これでなければアロハシャツと呼ばない!」という決まりがあるわけではありません。
リゾート地として開発が始まった頃からハワイの代表的なお土産として広く認知され、いまでは世界中でアロハシャツは愛される存在となりました。
アロハシャツの起源は和服!?

アロハシャツの歴史には日本からの移民および日本そのものが大きく関わっています。
サトウキビ産業の労働者として働いていた日本からの移民たちは、もともと「パラカ」という開襟シャツを愛用していました。木綿ガスリという江戸〜大正にかけて一般的だった和服に似ているという理由だったそうです。
ちなみに「パラカ」というのはもともとヨーロッパの船乗りたちが着ていたものだそうで、チェック柄であることが特徴です。そのうち日本から持ってきたその他の着物も「パラカ」風に再利用したい、と思うようになり、それがアロハシャツの起源となったといわれています。
また日本の着物を気に入った現地ハワイの人が、その生地でシャツを作ってくれと頼んだのが起源だという説もあるようです。
ハワイを代表するファッションになった理由

徐々に現地で人気が出てきた元祖アロハシャツ。農業だけではなく街のいろいろな職業に就くようになっていった日系移民の人たちは、この元祖アロハシャツを売るアパレル産業にも着手していきました。
その代表的なものが仕立て屋の「むさしや商店」。最も早い時期から和柄のシャツを手がけており、広告で「アロハシャツ」という言葉を初めて使ったのもこのお店だとされています。そして1936年にこのアロハシャツという名前はキング・スミスという洋品店のオーナーによって商標登録され、むさしや商店の作ったシャツが正式にアロハシャツとして売られることとなりました。
またこの時期、アロハシャツを主に生産していたのは他でもない、日本でした。織物文化が盛んだった京都や大阪でアロハシャツが輸出用に作られ、ハワイの地へと渡っていったのです。
時は流れて1950年代。アメリカ本土でハワイファッションの大ブームが巻き起こります。そのきっかけのひとつはハワイの地元民だったオリンピック金メダリストのデューク・カハナモクがハワイの観光大使として全米を回ったこと。彼の名前がついたアロハシャツは大人気となり、飛ぶように売れたそうです。
またもうひとつのブームがエルビス・プレスリーが映画『ブルー・ハワイ』でアロハシャツを着たことによって到来します。このことによってハワイを気に入ったセレブたちが次々とアロハシャツをファッションに取り入れ、ハワイ=アロハシャツというイメージを世界中に知らしめました。
現代でのアロハシャツの使われ方

このような歴史を辿り、アロハシャツは現在のような南の島を代表するファッションへと立ち位置を変えました。ハワイではフォーマルな服装として認知されており、ビジネスの場や高級レストランなどでも着用が可能です。
また結婚式やお葬式などでも着られる正装とされており、ただのお土産ファッションというよりはハワイの文化的な衣装としての認識のほうが強いことがわかります。むしろカジュアルな服装としてはTシャツのほうが一般的です。
フォーマルな場ではアロハシャツの着方に作法があり、たとえばお葬式のときは「万物の終わり」という意味をもつラウハラの葉の柄が入ったものを着なければなりません。また結婚式の場合は「結ぶ」という意味をもつマイレの葉の柄、旅に出る時や事業を始めるときはパンノキの木の柄のものを着るなど、アロハシャツの柄をTPOに応じて着分けるという文化があるのです。
アロハシャツとハワイアンシャツ

アロハシャツとハワイアンシャツ。どちらも一般的に使われている名称ですが、このふたつに具体的な違いはあるのでしょうか。
結論からいうと、シャツ自体に違いはまったくありません。ただ前述のようにキング・スミスという洋品店が商標登録をしたことから、「アロハシャツ」は商品名となります。厳密にはハワイアンシャツというジャンルのなかの、アロハシャツという商品、という認識になるわけですね。
しかし商品名のほうが一般名よりも有名になってしまったことから、現在ではアロハシャツという名前で広く知られているわけです。「宅急便」や「サランラップ」と同じ現象だといえるでしょう。
ヴィンテージアロハシャツというものがある!

日本においてアロハシャツは、基本的にカジュアルで安価なイメージがあります。しかしなかにはヴィンテージアロハシャツという、高価な種類があるということをご存知でしょうか?
そのなかでも特に価値があるとされているのは、生地がレーヨンまたはシルクで出来ているもの。またヤシの木から作られた「ココナッツボタン」と呼ばれるボタンのあるものも人気です。さらに「バンブーボタン」と呼ばれる竹で出来たボタンがついたものも大変希少性が高いとされています。
またそのほかにも貝殻を素材に作られた「シェルボタン」や金属で刻印やデザインの入った「古銭ボタン」を使ったものも。だいたい1930年代から1950年代にかけて作られたものがヴィンテージアロハシャツとされていますが、古さだけではなくその内容によって価値はさまざまです。奥の深い世界だといえるでしょう。
アロハシャツの代表的ブランド

次にアロハシャツの代表的なブランドについてご説明したいと思います。
ひとつはレインスプーナー。1956年にハワイで生まれ、2000種類ほどの手描きの柄やプリント生地を裏返した手法などで有名です。
生地は「スプーナークロス」と呼ばれるオリジナルのものを使用しており、綿55%・ポリエステル45%の混紡で着心地がよくシワになりにくいのが特徴です。
もうひとつはサンサーフ。前述のようなヴィンテージアロハシャツを取り扱うブランドで、抜染やオーバープリントという当時の手法を用いて整備をしています。
アロハシャツを「アートを着る」ものととらえ、プリントの鮮やかな発色などを再現するノウハウと技術を極めたブランドなので、マニアにはたまらないのではないでしょうか。
日本におけるアロハシャツ

最後に日本におけるアロハシャツの扱われ方についてご説明していきます。
日本では神奈川県の茅ヶ崎市や和歌山県の白浜町など、「東洋のハワイ」を掲げている地域がいくつかあります。そのような場所では自治体や駅でも職員がアロハシャツを着用しており、まるで現地のような光景が見られメディアでもたびたび取り上げられています。
また福島県いわき市にあるスパリゾート「ハワイアンズ」では宿泊客は浴衣ではなくアロハシャツを着用します。このような面白いやり方は全国各地の健康ランドなどでも見られるそうです。
最も南国の気候に近い沖縄県ではアロハシャツをモチーフにした「かりゆしウェア」というシャツが夏の軽装として普及しています。かりゆしウェアとはアロハシャツを少しシックにしたものですが、基本的にはそっくりです。しかし「沖縄の県産品で沖縄らしさを表現したもの」として沖縄県でブランディングされており、柄についても沖縄で見られる花や動物などが使われています。
まとめ

今回はアロハシャツの成り立ちやその種類、取り扱われ方についてご説明させていただきました。これだけ世界的に有名な商品を日本からハワイに移住した人たちが作り出し広めたということを、日本人はもっと誇ってもいいかもしれません。
またヴィンテージアロハシャツという世界があるのも面白みのひとつです。それを取り扱う「サンサーフ」というブランドは当時の技術をそのまま用いて、柄のプリントなどを再現しているのも驚きです。
この記事を通してアロハシャツについて知ることで、ハワイに対する興味がもっと深まっていただけましたら幸いです。